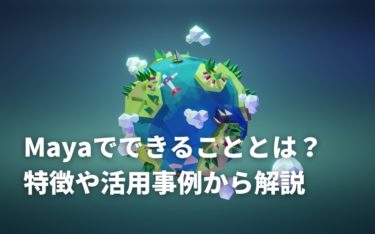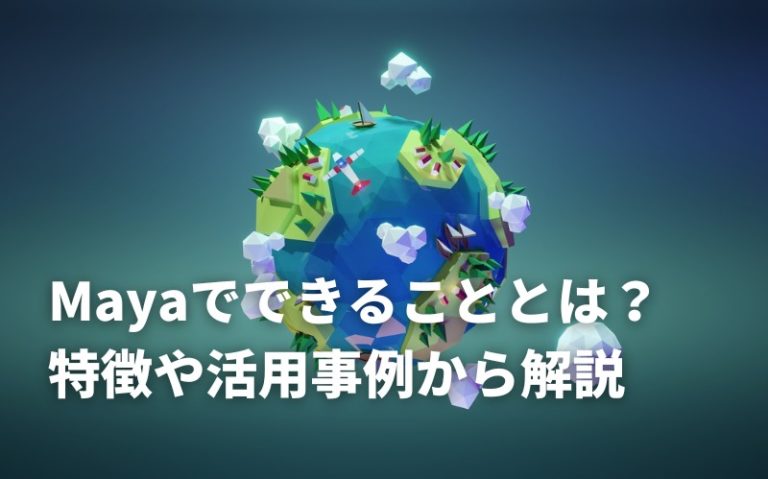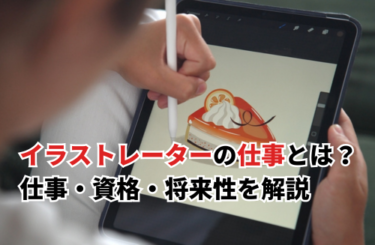3DCGに取り組んでいる、または興味がある方であれば「Maya」というソフトウェア名を聞いたことが無い方は少ないのではないでしょうか。
世界的に圧倒的なシェア率を誇る3DCGソフトウェア「Maya」。
導入を考えている方や、Mayaでできることを知りたい方に向けて「特徴」「できること」「活用事例」の3つの項目でMayaを解説していきます。
Mayaの特徴とは
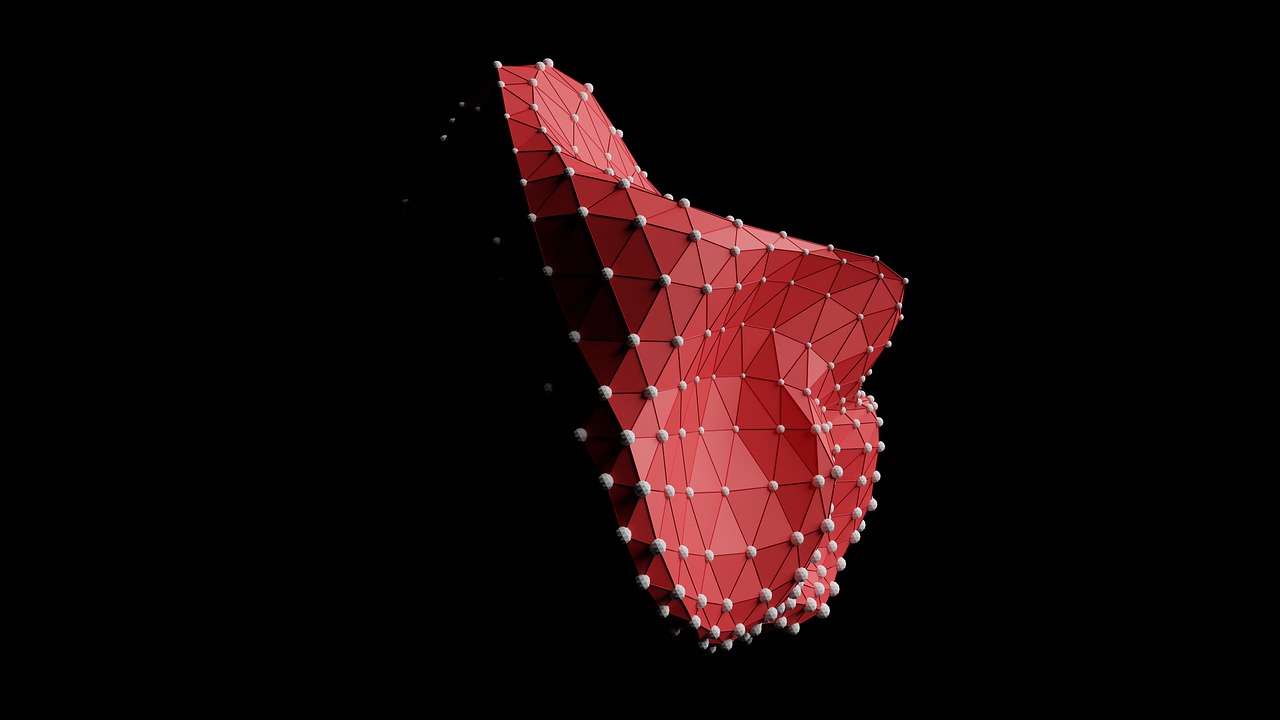
MayaはAutodesk社から出ているハイエンドの3DCGソフトウェアです。
ハリウッドでも使われているプロ仕様の性能を持っています。主に映像(アニメーション・ゲーム・TV・映画・CM等)で使用されており、とくにVFX界隈では圧倒的なシェア率を誇ります。
同じくAutodesk社から出ている3ds Maxと比較されることが多く、Mayaと3ds Maxの世界的なシェア率は約半々です。
Mayaと3ds Maxの違い
Mayaと3ds Maxの大きな違いとして「拡張機能の違い」があります。
3ds Maxはプラグインが豊富で、プラグインを利用することで様々な機能を利用しやすい点が優れています。
それではMayaはプラグインがたくさんないからそんなに機能がないの?と思われるかもしれませんが、Mayaはスクリプトでプログラムを書けばいくらでもカスタムできるのです。
プラグインを利用するよりハードルは上がるものの「プログラミングができればいくらでもカスタマイズできる」という自由度の高さが魅力です。
3ds Maxの概要に関しては下記記事で詳しく解説しています。
Mayaの価格と対応OS
Mayaの対応OSはWindows・Mac・Linuxです。
価格については永久ライセンスは無く、サブスクリプションで提供されます。
価格は契約年数によって変わりますが、下記のようになっています。
- 3年契約/815,100円(税込)
- 1年契約/286,000円(税込)
- 1ヶ月契約/36,300円(税込)
無償体験版(30日間)や、30日間の返金保証もあります。(価格や販売形式は2022年9月時点のものです)
Mayaでできること

Mayaは3DCGソフトウェアとして多くの機能が備わっています。活用事例を見てもわかる通り、ひとつのジャンルに留まりません。
また、Autodesk社の製品をすでに使っている場合は互換性が高く使いやすいです。
具体的にできることを並べると
- 3Dアニメーション
- 3Dアニメーションキャラクターの作成
- モデリング
- リギング
- シミュレーション
- レンダリング
- モーショングラフィックス
です。VFXで圧倒的な支持を得ていることから、VFXであれば機能的にも業界的にもとくに使いやすいソフトウェアと言えます。
レンダリングについてはMaya2017から標準搭載されているArnoldというソフトを使うことにより、さらにクオリティが上がります。
質の高いプラグインが用意されていることもほかの3DCGソフトと一線を画すでしょう。
もちろん、プログラミングでスクリプトの開発ができるのであればオリジナルのツールを作って使うことも可能です。
そして、映像作品だけではなくシミュレーションができるソフトとしても評価が高いのがMayaです。
製品やイベントのシミュレーションにも使用され、あらゆる業界のDX化をすすめています。
豊富で高性能な機能とカスタマイズの自由さにより、3DCGを必要とする場であれば個人から企業まで、どんな場でも活躍するソフトウェアです。
Mayaの活用事例5選
実際にMayaがどのように使われているのか、活用事例を見ていくとMayaの機能の高さがよくわかります。
ここでは「映像」「ゲーム」「シミュレーション」の3つに分けて、Mayaの活用事例を紹介します。
映像業界の活用事例
映像業界でのMaya活用事例はこちらがあります。
①MARVEL映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス」

MARVEL映画で有名な「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス」は、実はモデリングがほとんどMayaで行われています。
重要な戦闘シーンでは、敵であるモンスターのたるんだ皮膚のシミュレーションや、コスチュームのクロスシミュレーションの作成時にMayaのクロス機能を使用。
アニメーション部分では、主要キャラクターのキーフレームアニメーションや、モーションキャプチャを使ったアニメーションの仕上げに使われています。
シェーディング・ライティング・レンダリングにはArnoldをカスタマイズして使用。専用に開発されたソフトウェアを使ったライティングやジオメトリの変換も、Arnoldで使えるようにしています。
②映画「海獣の子供」
漫画が原作のアニメーション映画作品。原作そのままの絵が動いてると評判になった圧倒的な映像が特徴です。作画であれば簡単にできることこそCGで挑戦し、3DCGを「便利なツール」というだけではなく「新しい表現ができるツール」として使用しています。
原作のタッチを表現するために、テクスチャをCGモデルに貼り込んで表現。微妙な凸凹や水滴などの繊細な表現はCGだからこそできた表現です。
Mayaを使い、作画とCGのハイブリットな融合に挑戦しています。
③「映画ドラえもんのび太の新恐竜」
フォトリアルとは違う図鑑イラストそのままの恐竜が動く、という世界観を表現するためにMayaを使用しています。アニメ的なデフォルメとリアリティのある表現のバランスは3DCGだからこそ。
恐竜の羽毛表現には、Mayaの「XGen」という機能を使用。「XGen」はヘア全般を作成したり、毛が自然になびくためのアニメーションを加える機能です。この機能によりリアルすぎない、デフォルメされた「ビジュアル」の恐竜がデザインされました。そしてグルーミングというツールで、毛流れなどの「動き」を調整。
映画のメインである恐竜の「ビジュアル」と「動き」両方でMayaが活用されています。
ゲーム業界の活用事例
次にゲーム業界でのMayaの活用事例を紹介していきます。
「バイオハザード7 レジデント イービル」
物理ベースのレンダリングに移行、自社用のゲームエンジン開発など、過去作から技術面を一新した作品。
フォトグラメトリーという、写真素材=完成品とも言える3Dデータの構成では、形状の微調整にMayaを使用。そして、フォトグラメトリーを使用しないモデル(たとえば実在しないクリーチャーなど)はMayaのモデリング機能を使って作られています。使い勝手のいいUVエディタはとても役立ったようです。
動きの面でも、モーションキャプチャーから「映える」アニメーションになるまでMayaを使って調整。
開発された自社用のゲームエンジンとMayaを併せて使った制作方法が可能だったのも、Mayaのカスタマイズの自由さが大きく関わっているでしょう。
シミュレーション活用事例
そしてシミュレーション業界でのMaya活用事例は下記になります。
「アパレル業界でのDX化を促すGOOD VIBES ONLY」
アパレル業界では在庫管理やそれに伴う廃棄問題が業界的に大きな問題です。
株式会社GOOD VIBES ONLYではアパレル業界の問題を無くすためにDX化を促進。その現場でMayaは使われています。
注目したいのは「デジタルサンプル」です。アナログで行っていたサンプル作成を、すべてデジタル化することでスピードアップとコストの削減に成功しています。
アナログの場合、工程にかかる人数や日数は少なくありません。ですが、工程すべてをデジタルにすることで、だいたい1日か2日で終わるようになったとのこと。
デジタルであればサンプルのために、多くのカラーバリエーションを現物として作る必要もありません。デジタル上で色の確認ができるため、採用されなかったカラーバリエーション分のサンプル廃棄がなくなります。
そして、Mayaだからこそできることに「リアリティのある質感表現」があります。服ならではの、布やファーの質感を表現するためにMayaが使われています。物理的に正確なシミュレーションによって、リアリティのある服を表現することが可能となっているのです。
モデルを使ったサンプル撮影も、リアルとデジタルを合わせた撮影方法。実際に撮影した人物にデジタルの服を合成する方法です。人物撮影時のライティング環境をMaya上で再現し、合成による不自然さを無くしています。
Mayaでできることのよくある質問
それでは実際Mayaでできることの中でよくある質問に回答してみました。
多くの業界で使われているMayaでできることまとめ
今回はMayaの特徴とできること、活用事例について解説しました。
できることが幅広く、カスタマイズもできるため多くの業界で使われていることがわかります。
導入を迷われている方、使用感を試したい方はぜひ一度、無料体験版で実際にMayaを触れてみてはいかがでしょうか。
こちらの記事を読んでMayaに興味を持たれた方はProSkilllのMayaセミナーの受講をおすすめします。
実務に即した課題をトレーニングする実践形式のセミナーなので、初心者の方でも2日間でMayaを業務で活用できるようになります。
受講スタイルが会場またはウェビナーを選択することが可能なのも魅力的で、ご自身のライフスタイルにあった受講方法をお選びくださいませ。