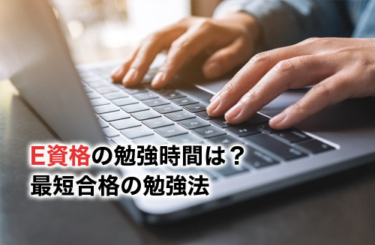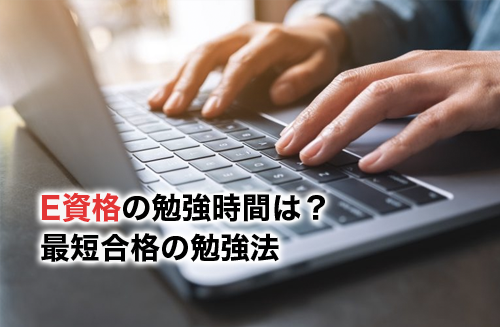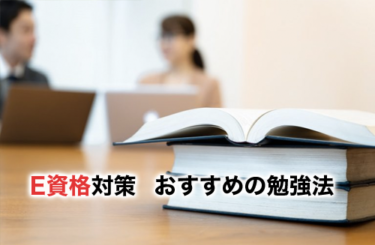E資格は近年話題のディープラーニングに関する資格ですが、合格までに必要な勉強時間はどの程度なのでしょうか?
今回は、合格者の勉強時間や最短で合格するためにおすすめの勉強方法について解説します。
E資格とは
E資格の「E」は「Engineer」の略で、日本ディープラーニング協会(JDLA)が認定するディープラーニングを実装するエンジニア向けのスキルを証明するための資格です。
まずは、試験日程や受験資格、試験範囲など、E資格の基本情報について解説します。
試験日程
E資格の試験日は、毎年8月と2月の年2回です。
詳しい日程は、一般社団法人日本ディープラーニング協会公式サイトを確認してください。
また、後述しますが、E資格は試験範囲(シラバス)の改訂が頻繁に行われます。
そのため、どの受験日程がどのシラバスなのかを把握しておかないと、勉強した範囲外の内容が出題されてしまうことになるので注意しましょう。
受験資格
E資格の受験のためには、「JDLA認定プログラム」を修了する必要があります。
JDLA認定プログラムとは、JDLAが認定するさまざまな会社が開講するディープラーニングを対象としたセミナーです。
E資格を主催するJDLAがシラバスの内容や講義内容の充実度などを審査するため、JDLA認定プログラムを受講することで、E資格合格に大きく近づくことができます。
試験範囲
E資格の試験範囲は、頻繁に改訂があります。
ディープラーニングは、ITやAIなどの近年人気の技術分野の中でも技術開発が盛んな分野です。
日々技術が進歩していく中で、エンジニアに求められるスキルや知識も日々変化していくため、それに合わせてE資格のシラバスも変更されるのです。
実際に受講する際には、最新のシラバスの内容をよく確認してから対策・受験するようにしてください。
ここでは、最新版のシラバスの内容について紹介します。
なお、詳細はE資格の試験範囲から確認してください。
数学的基礎
応用数学では、ディープラーニングと関連の強い次の2分野が主な試験範囲になります。
- 情報理論
- 確率・統計
機械学習
機械学習については、主に次の分野が試験範囲となります。
- 機械学習の基礎
深層学習の基礎
深層学習の基礎では、次の分野が試験範囲となります。
- 順伝播型ネットワーク
- 深層モデルのための最適化
- 深層モデルのための正則化
- 畳み込みニューラルネットワーク
- リカレントニューラルネットワーク
- Transformer
- 汎化性能向上のためのテクニック
深層学習の応用
- 画像認識
- 物体検出
- セマンティックセグメンテーション
- 自然言語処理
- 生成モデル
- 深層強化学習
- 様々な学習方法
- 深層学習の説明性
開発・運用環境
開発・運用環境としては、次の分野が試験範囲となります。
- エッジコンピューティング
- 分散処理
- アクセラレータ
- 環境構築
G検定との違い
E資格とよく似た資格に「G検定」があります。G検定の「G」は「Generalist」の略称で、こちらも同じくJDLAが認定するディープラーニング向けのスキル証明に役立つ資格です。
E資格がエンジニア向けの資格だとすれば、G検定はビジネス向けのスキルという違いがあります。
また、E資格は後述する「JDLA認定プログラム」の受講が受験資格になりますが、G検定には受験資格などはありません。E資格に比べると難易度も低くなっています。
そのため、まずはG検定に合格して、ステップアップとしてE資格取得を目指すという方もいます。
E資格の難易度・合格率
E資格の難易度を理解するために、過去の合格率を見てみましょう。
| 開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2018 | 342 | 337 | 234 | 69.44% |
| 2019#1 | 396 | 387 | 245 | 63.31% |
| 2019#2 | 718 | 696 | 472 | 67.82% |
| 2020#1 | 1,076 | 1,042 | 709 | 68.04% |
| 2021#1 | 1,723 | 1,688 | 1,324 | 78.44% |
| 2021#2 | 1,193 | 1,170 | 872 | 74.53% |
| 2022#1 | 1,357 | 1,327 | 982 | 74.00% |
| 2022#2 | 917 | 897 | 644 | 71.79% |
| 2023#1 | 1,131 | 1,112 | 807 | 72.57% |
| 2023#2 | 1,089 | 1,065 | 729 | 68.45% |
| 2024#1 | 1,215 | 1,194 |
867 |
72.61% |
| 累計 | 11,157 | 10,915 | 7,885 | – |
この表からわかるように、過去の合格率は63~78%程度であり、難しい資格で内容に思えるかもしれません。
しかし、次のデータを見てください。
| 職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
| 営業・販売 | 25 | 2.88% |
| 企画・調査・マーケティング | 36 | 4.15% |
| 経営・社業全般 | 6 | 0.69% |
| 経営企画 | 6 | 0.69% |
| 研究・開発 | 377 | 43.48% |
| 情報システム・システム企画 | 228 | 26.30% |
| 生産・製造 | 48 | 5.54% |
| 総務・経理・人事 | 7 | 0.81% |
| 学生 | 57 | 6.57% |
| その他 | 77 | 8.88% |
| 総計 | 867 | 100.00% |
ここからわかるように、職種としては「研究・開発」と「情報システム・システム企画」が合わせて69.78%と大半を占めており、基本的にはITを専門とするエンジニアが受験生のほとんどです。そんな中で7割程度の合格率ということなので、そう高い数字ともいえないでしょう。
合格率が高めだからといって安心していると、痛い目にあうかもしれません。
E資格を取得するメリット
そんなE資格を取得することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、E資格を取得するメリットについて解説します。
AIスキルの証明になり就職活動で有利になる
ディープラーニングは現在注目を集めている分野で、技術展開が目まぐるしく、ディープラーニングの知識を有するエンジニアはどんな企業でも活躍できるでしょう。
そんな現代においては、転職活動の際にディープラーニングに関するスキルをアピールできる数少ない資格といえるため、面接や書類選考の際に他の方との差別化につながる可能性があります。
合格者専用のコミュニティで人脈を広げられる
E資格に合格すると、合格者専用のコミュニティCDLE(Community of Deep Learning Evangelists)に参加できます。
そこでは、最新のAIやディープラーニングにおける市場動向や最新情報を得ることができるので、絶えず最新の知識を習得できます。
また、コミュニティ内のチャンネルに入って議論することによって、自分の興味のある分野から人脈を広げることもできます。
合格者限定イベントに参加できる
E資格またはG検定に合格した方のみが参加できる「COLE DAY」というイベントがあります。
このイベントはオンラインにて年間2回ペースで開催されており、懇親会も設けられているため、このイベントを通じて学びを通して人脈を広げることができます。
E資格の勉強時間
E資格に合格する人は、どのくらいの時間勉強しているのでしょうか?
ある統計では、平均で60~100時間勉強しており、多い方で200時間の勉強時間となっているようです。1日あたり4時間勉強すれば、約1ヶ月で100時間になるので、勉強時間は長いと言えるでしょう。
もし勉強時間が足りずE資格に落ちてしまったら…と思う人はこちらのサイトも参考にしてください。
E資格の勉強時間を短縮するコツ
100時間近く勉強する必要があるE資格ですが、勉強時間を短縮するためにはコツがあります。
ここでは、プログラム特有の方法について解説します。
全体像を把握する
「木を見て森を見ず」ということわざがありますが、これは一般的には悪い意味で使われます。
しかし、未知の学習を進める上では非常に重要なファーストステップです。
これができていないと、いくら勉強していても理解度が上がりません。
まずは、その分野について全体的に俯瞰してみます。
E資格でいえば、まずはシラバスだけをザーっと流し読むようなイメージです。
これをすることで、これから勉強する分野の全体のボリュームと関連性についてざっくり理解できます。
その後に細かな学習に入ることによって、「この分野は、あとで出てくるこの分野のために学んでいるんだな」とつながりを理解することができるため、モチベーションが保ちやすく、関連づけて覚えられることで定着度が増します。
E資格に限らず、一般的にどんな学習についても重要なことなので、実践してみると良いでしょう。
反復して苦手な箇所を洗い出す
資格の合格のためには、苦手な分野を残しておくことは非常に危険です。
得意な分野や好きな分野があるからといって、その分野ばかりを勉強していても点数は一向に伸びません。
合格のためには、苦手な分野を見つけ、その分野に注力して苦手を克服することが重要です。
したがって、まずは苦手な分野を見つけ出し、その分野については反復して理解度や定着度を上げていく努力が必要です。
早めに手を動かして実際のコードに触れる
プログラミングやITの勉強をしたことがある方ならわかるかと思いますが、プログラミングは理論を理解するよりも、使い方に慣れて実際にコードに触れて失敗しながら覚えていく方が早く、わかりやすい場合もあります。
「こんな入力をすると、どんな出力が得られるんだろうか」と考えて理屈を追い求めるよりも、チャチャっとテストコードを作って実行してしまった方が一目瞭然であり、確実です。
また、実際にコードを書いてみて思ったように動作しないことがあれば、その理由について考えているうちに自然といろんなことを勉強できるため、学習効率がより高くなるといえます。
したがって、E検定のようにエンジニア向けのスキルを試されるような資格の勉強では、実際のコードに触れることが合格の近道になります。実際のコードの触れ方がわからない場合は、外部セミナーを受講することをおすすめします。
E資格の勉強に効果的な講座とは
ここからは、勉強時間を短縮するために効果的なJDLA認定のE資格対策ディープラーニング短期集中講座というセミナーを紹介します。
E資格の勉強を効率化できる?
E資格対策ディープラーニング短期集中講座は他のセミナーや講座・スクールと比べて非常に短期間・短時間でE資格を学ぶことが可能です。
さらにJDLAの認定講座となっているので、勉強とともにE資格の受験資格を得ることができる数少ない講座となっています。
この2点を合わせると、かなり時短になりE資格の勉強時間を効率よくすることができるでしょう。
AIエンジニアのプロから教わることができる
E資格対策ディープラーニング短期集中講座ではAIエンジニアとして活躍するプロから教わることができるので、E資格が終わってもその知識を仕事に活用することができます。
分かりやすい内容でしっかり理解をすると、結果的に勉強時間が短くなる可能性もあります。
E資格の勉強時間はどれくらい? まとめ
E資格の勉強時間は60~100時間程度といわれていますが、さまざまな方法で勉強時間を短縮することができます。
AI研究所のE資格対策ディープラーニング短期集中講座では、事前情報のない状態から4日間で必要な知識の習得ができるので、かなり効率のいい学習方法といえます。
気になる方はチェックしてみてください。
企業の成長にはDXやAI活用が欠かせません。AIについての知識が不足している場合、どのように進めればよいのか悩まれることもあるでしょう。
AIプロジェクトを進めるために必要な要件を相談しませんか?
企業のニーズに合わせたAIコンサルティングを提供しており、専門家がお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください。