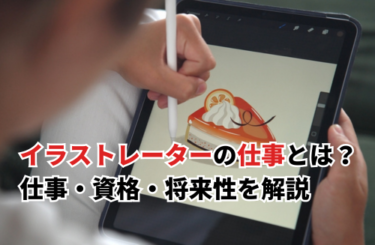CAEとは、設計の際にコンピュータ上でシミュレーションを行うシステムのことです。
製造時間の短縮につながるので、さまざまな大手メーカーでも導入されはじめ、将来性のある技術として注目されています。
今回は、そのようなCAEに関する資格の種類や資格の取得方法について紹介していきます。
CAE解析関係の資格一覧
CAEの資格取得を考えているが、どのようなものを取得したらよいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、CAE解析に役立つ資格3つを一覧でまとめました。
CAE解析の資格①技術士機械部門
機械設計や設計工学などといった、工学全般に関する知識を問う国家資格の1つである技術士機械部門。
社会的認知度は高いですが、合格率が低く、2次試験の合格率は10%前後と大変難易度の高い資格です。
試験は、公益社団法人日本技術士会によって年1回実施され、合格までの平均受験回数は4回から5回となっています。
資格取得までに時間を要する方が多い傾向なので、効率よい勉強方法やきちんと計画を立ててからの学習をおすすめします。
CAE解析の資格②基本情報技術者
コンピュータに関する知識に対して不安を感じていませんか。
実は、CAE解析にはITの理解が必須です。
なぜなら、シミュレーションにはコンピュータやソフトウェアを利用する必要があるためです。
基本情報技術者は、プログラミングだけでなく、I Tに関する理解しておくべき基本的な知識を体系的に学習できる資格です。
年齢や実務経験に関わらず、試験を希望するすべての人が受験可能となっていて、気軽に挑戦できるのも魅力ですね。
CAE解析の資格を取るにあたり、パソコンに関しての知識やスキルが必要だと思った人はこちらの資格を取得すると良いでしょう。
CAE解析の資格③計算力学技術者
CAE解析には、数値解析の知識が欠かせません。
そのような知識を学びたいときには、計算力学技術者の資格取得がよいでしょう。
計算力学技術者とは、変形や振動などの力学に対して物がどのように反応するかという解析をする技術者のことです。
一般社団法人日本機械学会が試験を行なっており、
- 固体力学分野
- 振動分野
- 熱流体力学分野
といった3つの分野から成り立っています。
そして、レベルは初級から上級アナリストまでの4段階に分かれており、自分に合ったレベルを選択できますよ。
それぞれのCAE資格の取り方

CAEに関する3つの資格を理解できたら今度はそれらについて取り方を詳しく学んでいきましょう。
技術士機械部門の取得方法
技術士機械部門に合格するには、各科目50%以上の正答率を目指す必要があります。
まず、公益社団法人日本技術士会のホームページで過去問をダウンロードし、それらを利用することで問題傾向を把握してみましょう。
詳しい解説が欲しい場合には、市販の参考書を購入し勉強してみるのもよいですし、通信講座の利用もおすすめです。
特に通信講座は、好きな時間に受講できたり、プロの講師がわかりやすく解説してくれたりする大きなメリットとなるはずです。
なお、技術士機械部門は2段階に試験が分かれています。
2次試験については、4年から7年の実務経験を積まなければ受けられないことは注意しましょう。
基本情報技術者の取得方法
基本情報技術者の試験は2つに分かれており、午前試験ではIT関連の基礎知識、午後試験ではその知識をさらに応用できるかどうかを問われます。
この資格を取得するには、午前と午後の内容に応じた対策が重要です。
午前試験の対策では、どの分野においても過去の試験と同じテーマの問題が出題される傾向なので、過去問の反復を心がけましょう。
午後試験の対策は、アルゴリズムとプログラミングの配点が高い科目を中心に勉強することです。
それらの内容を重点的に学習できる問題集もたくさん存在しています。
チェックしてみましょう。
また、勉強をはじめる際は、午後についての内容からではなく、午前の対策から行う方がスムーズに進みます。
午後試験の問題は応用がメインのため、午前試験の内容を理解できないと難しいと感じるはずです。
計算力学技術者の取得方法
計算力学技術者は初級の場合試験がなく、公認CAE技能講習会を受講して認定審査が通れば合格となります。
この講習は大学や企業などのさまざまな場所にて催されているので、ぜひ近くで実施されているかどうか確認してみてください。
一方で2級からは試験があります。
学習方法としては認定試験対策講習会に参加したり、公式テキストの標準問題集を用いて学んだりすることが方法として挙げられます。
対策講習会は、先着順です。
申し込みを考えている方は、こまめに情報を見ておきましょう。
専門家がわかりやすく教えてくれることで、自分で学習するよりもさらに理解が深まるはずです。
CAEで資格を取るときに便利な知識

CAEに関する資格を取る際に得ておくべき知識が事前に知れたら嬉しいですよね。
ここでは、CAEについて知っておくべき知識を3つ紹介していきます。
①CAEソフトウェアの知識
CAEソフトウェアの使い方を知っておくと、計算力学技術者の試験で役立ちます。
2級以上を取得するには、CAEソフトウェアの使用経験が必須です。
CAE解析に関するソフトは高額なイメージで、到底購入はできないと感じている人もいるでしょう。
実は、CAEソフトは無料で気軽に試せるものが色々あるので、そういった場合非常に役立ちます。
無料ですと、機能や使用期間に制限はあるかもしれませんが、簡単なCAE解析であれば十分対応できます。
Calculixといった有限要素解析ソフトウェアや、構造解析が可能なCodeAsterに触れておくと、CAEについてさらに理解を深められるに違いありません。
②大学卒業程度の工学に関する知識
技術士機械部門や計算力学技術者2級の資格を取得する際は、大学卒業程度の工学の知識を持っていると試験で有利に働くはずです。
工学系の大学を卒業した後、これらの資格に関する過去問や問題集を見ると、大学時代に習った知識が出題されていると感じるのではないでしょうか。
学生時代に力学などを専攻していた場合は、使用していた大学生向けの参考書を調べてみるのも理解が深まりそうですね。
一方、学生時代工学を専攻していない方でも問題ありません。
自分で大学生向けの参考書を購入できるので、書店で自分に合ったものを探してみてはどうでしょうか。
③計算力学技術者認定試験付帯講習会の免除規定
計算力学技術者の資格認定において、通常は付帯講習会を受ける必要があります。
しかし、指定のセミナーを8割以上受講済みの場合は、受講証明書のコピーを提出することで付帯講習会の受講が免除になる可能性があります。
対象の講座は、サイバネットシステムの
- Ansys CFX ベーシックセミナー
- Ansys Mechanical APDL 入門セミナー
などです。
また、CAEユニバーシティでは
- CAE強度設計のための力学講座
- FEM原理実習
が、付帯講習会に替わるものとして認定されています。
受講証明書を紛失しても再発行はできないので、これらのセミナーを受講した覚えがあるときは書類を大切に保管しておくことをおすすめします。
CAEの資格は何がある?種類や取得方法のまとめ
CAEの知識や資格を取得しておいて損はありません。
製造のDXが進むにつれて、これらの重要性は高まってきており、解析エンジニアといったCAE系の職業の転職にも有利に働くでしょう。
ポイントを押さえながらきちんと対策を行うことでスムーズに資格が取れるとよいですね。