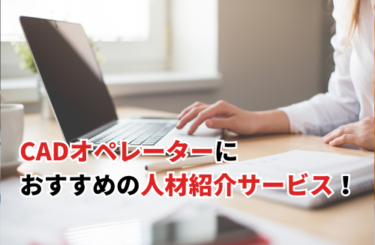PLMやPDMを導入することによって、業務の効率化やコスト削減に役立てることができます。PLMとPDMは製品に関わるシステムであるという点は同じですが、それ以外の点は微妙に異なります。それぞれのシステムについて理解を深め、自社の業務を最適化できるものを選定することが必要不可欠です。
ここでは、PLMとPDMの違いやそれぞれの機能、メリット・デメリットや導入時のポイントなどについて詳しく解説します。
PLMやPDMの導入を考えているけど最適な選定方法を理解していない方や、PDM・PLMにどのようなメリットがあるのかわからない方は、ぜひ参考にしてみてください。
PLMとPDMの違い
PLMとPDMは非常によく似ていますが、PLMは製品の企画から販売までのプロセスを対象とするデータ管理システムのことを指します。PDMは開発・設計データの管理に特化したシステムです。
つまり、PLMが製品のライフサイクルのすべてを対象としているのに対して、PDMは製品開発の一部分のみを管理しているという違いがあります。ただし、ベンダーによってはPDMなのに企画や販売を提供している場合もあるため、導入前には事前のリサーチが必須です。
PLMとは
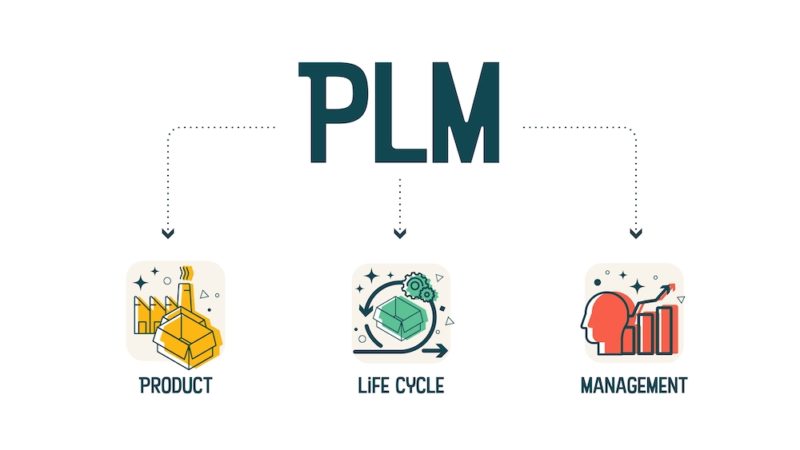
PLM(Product Lifecycle Management)は製品の企画から廃棄までの、すべての段階の情報を企業内で管理するためのシステムです。そのままピーエルエムと読みましょう。PLMを導入することで業務効率の向上や開発コストの削減などが達成できるようになります。
PLMが生まれたのは1950年代で、国防総省によって開始された構成管理が基になっています。1985年頃には一般企業に導入されていきました。製品の図面やデザインを企業内で共有し、業務効率の向上が図られています。
PLMについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
PLMシステムの機能には何がある?
PLMシステムの主な機能には、
- 企画で活用される機能
- 設計で活用される機能
- 製造で活用される機能
- 保守で活用される機能
があります。企画段階では顧客の要求を受けて自社で作れるかを判断していきます。
PLMシステムにはポートフォリオ管理機能などが搭載されているので、ポートフォリオを最適化でき効率化が可能です。設計段階では製品のモデリングやシミュレーション機能が用いられます。
他に
- データ解析
- 開発スケジュール
- 3Dデータ管理
などの機能も備えています。
製品ライフサイクルにおいて実際に製品を製造する段階では、
- 型の加工の設計
- 工場ラインのシミュレーション
- 電子作業指示書の機能
が役立ちます。これらの機能を利用することによって、製品の製造プロセスにおける遅滞やミス、製品不良の発生を防ぐことができます。
製品の完成後、製品の品質を良好な状態に維持するために、保守を行う必要があります。保守の段階ではPLMシステムの機能は
- 部品管理
- サービス管理
- 修理管理
などを活用します。アナログの手法ではなくデジタル化されたITシステムによって管理することで迅速な対応が実現するのです。
PDMとは

PDM(Product Data Management)システムとは、CADやBOMなどの設計工程で発生するデータを一元管理するシステムです。そのままピーディーエムと読みましょう。設計部門と他の部門との連携を強化することによって、生産性の向上を図ります。
PDMシステムを導入することで、製品のライフサイクル全体を最適化することが可能です。以下では、PDMシステムに搭載されている機能を紹介します。
データ管理機能
設計データの
- CAD管理
- 図面管理
- ドキュメント管理
- 部品表管理
- 設計変更管理
の一元管理をする機能です。関連性のあるデータをすべて紐付けられるため、膨大な量でも簡単に管理可能です。またデータへのアクセス権も設定できます。PDMはすべてのデータを管理できるので、外出先や異なる事業拠点からデータの確認・共有が可能です。
ワークフロー機能
設計部門の中で発生するワークフローを可視化する機能が、PDMには備わっています。ワークフローを可視化することで、社内での確認依頼や承認などといったプロセスはオンラインで実施可能です。ワークフローに沿った形で仕事を進めるように設定可能なので、ワークフローの標準化がしやすいこともPDMの特徴の1つです。
データ検索機能
データ検索機能を利用することによって、管理するファイルが多い環境においても業務効率の向上を図ることが可能になります。検索はファイルの名称や種類などの条件を打ち込むことで行います。PDMごとに検索機能のデザインが違うので、PDMを選ぶ際は注意が必要です。
セキュリティ強化機能
PDMにはセキュリティ強化機能が存在します。セキュリティ強化機能とはアクセスできるファイルを制限したり、編集や削除といった操作を制限したりすることを指します。従業員が担当している製品やプロセスに応じて、アクセス権限を付与するといった使い方をします。
PDMについては下記記事でさらに詳しく解説しています。
PLMのメリット

PLMには主に3つのメリットがあります。
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
1.データをもとにして製造できる
データをもとにした製造プロセスを実行できる点は大きなメリットです。PLMではBOMや製品情報の管理が行える上、必要な情報を検索機能で発見できます。
また、過去製造された製品の情報をもとに新製品の開発に活かせるため、工期短縮にもつながるでしょう。
2.変化に対応しやすい
PLMを活用すれば、製品情報やBOM、作業工程などをデータで管理できます。たとえば、顧客からフィードバックを受けた場合や市場の変化によって商品の売れ行きが怪しくなった場合に、管理者がデータを書き換えて社内全体に共有することで、プロモーション性が高まり顧客の購買を促進させられるでしょう。
また、製品のライフサイクル全体を一元管理すれば、書類を作成して上司に承認をもらうなど無駄な作業が発生しないため、本来割くべき業務に力を注げます。顧客のニーズを理解してから製造までにかかる時間を短縮でき、時代の変化に対応しやすい点もメリットです。
3.「QCD」を高められる
QCDとは、
- Quality(品質)
- Cost(コスト)
- Delivery(納期)
のことで、製造業では欠かすことのできない3要素となります。競合に勝つためにはそれぞれを最大化し、「良い」製品を「低コスト」で、「素早く」製造することが求められます。
PLMには、製品のライフサイクル全体を管理できる機能が備わっており、PLMを駆使して適切に管理することで、QCDを向上させられるのではないでしょうか。また、管理された各プロセスの情報をリアルタイムに共有できるため、QCDを高める際に変更点が生じた場合も、データをスムーズに活用できます。
PDMのメリット

PDMには、主に次の6つのメリットがあります。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
1.生産性向上に役立つ
PDMを活用すれば、更新のタイミングがずれることで確認しているデータが異なるといった問題を解決できます。PDMではデータをリアルタイムで共有できるため、どのデータが最新情報なのか、どの情報を最新版とするのかなどが把握できます。
また、PDMを活用すれば、メールでデータを送信する必要がありません。ツールに遠隔地からアクセスできるため、セキュリティ性を高めた状態でデータを共有できます。
2.データをリアルタイムで共有できる
PDMの導入によって情報の共有性や検索性が高まるため、行わなければならなかった書類探しや申請・承認作業などにかかる時間を削減できます。また、その結果、本来行うべき業務に時間を割けるため、生産性向上にもつながります。
3.ワークフローを可視化できる
わかりにくいワークフローが設けられていれば、スタッフに浸透せず、ワークフローを遵守してもらうことが難しいでしょう。しかし、PDMを使うとワークフローをシステム上に設定でき、チェックポイントを設置して申請・承認作業を実行できるようになるため、スムーズにワークフローを浸透させられます。
4.データの再活用が容易である
PDMには、主に次の2つの効果があります。
- データを一元管理できる
- 検索性が向上する
そのため、検索で過去データをまとめて探し出せるため、過去データの再利用がスムーズになります。具体的には、過去製造した製品のデータを検索、新製品に反映したり、過去販売されていた製品の売れ行きを分析し、新たな製品に反映することも可能です。
5.データの一元管理ができる
PDMツールを導入すれば、必要な情報をすぐに探せるため、データ探しに工数を割く必要がありません。情報検索に時間をかける必要がない点は大きなメリットでしょう。
6.クレーム対応がスムーズである
顧客からクレームが来た場合、部品を製造している会社に問い合わせたり、不具合が発生した部品を購入した日時を確認したりと、さまざまな手間が発生していました。同様のクレームであれば同じ対処法を取れますが、まったく異なるクレームが来たときには再度問題特定に時間を割く必要があるでしょう。
一方で、PDMを活用すれば「部品がいつ変わったのか」「不具合が発生した部品を購入したのはいつか」という情報が把握できます。原因究明にかかる時間を短縮できるため、クレーム対応にも役立ちます。
PLMの導入方法・手順
PLMの導入においては、意識すべきポイントがあります。
ここでは、PLMの導入において意識すべきポイントを導入手順に沿って紹介します。
1.PLMで行う業務を明確にする
最も重要なことは、PLMで行う業務を明確にすることです。目的に沿った適切なツールを用意しなければ、導入しても自社の求める効果を発揮しないことがあります。
「どのような業務範囲で、誰が、どこで使うのか」など、活用シーンを明確にしてから導入を進めましょう。
2.自社に最適なPLMシステムを選ぶ
PLMで行う業務内容が明確になったら、自社に最適なPLMシステムを導入しましょう。
PLMシステムの中にはさまざまな機能が搭載されているものから、特定の機能に特化したものまで、幅広いシステムがあります。また、用途によってカスタマイズできるものもあり、そういったシステムを導入することで、自社にとって最適な機能をコストを抑えて利用できます。
3.試しに導入する
PLMを導入する場合、いきなり社内全体に浸透させることはおすすめできません。PLMシステムをいきなり導入してしまうと、問題点が生じたときに解決するのが難しいためです。
トライアルを利用し特定の部署にのみ活用して、本当に効果を得られるのか確かめながら導入を進めていくと良いでしょう。
4.利用者とコストの関係を常に考え続ける
利用者とコストの関係を常に考え続けることも重要なポイントです。
たとえば、特定の部署の数人しか活用しない場合に、豊富な機能を搭載しているシステムを導入しても得られる効果は薄いでしょう。また、逆に多くのスタッフが活用するにもかかわらず、専門的すぎるシステムを導入すると、社内にシステムが浸透していきません。
「利用者がどのくらいいるのか」「どのくらいのコストが妥当か」を考えながらツールを導入しましょう。
PDMの導入方法・手順
次に、PDMの導入方法や手順について解説していきます。
1.問題点を抽出する
最も重要なことは、問題点を洗い出すことです。まずは、自社のデータ管理においてどのような問題を抱えているのか、確認し、導入に踏み切ることが大切です。
また、導入時は上層部だけで決めるのではなく、現場のメンバーの意見をヒアリングしたりアンケートを取ったりして、現場で役に立つのかを考えましょう。
2.経営陣と現場の問題意識を共有する
現場のメンバーの意見に頼ることも重要ですが、それだけでなく経営陣が方針を定めることも重要です。「このような問題を感じており、改善したい」と経営陣が現場に伝えれば、現場が感じている思いや問題点を感じてくれるはずです。
3.試しに導入する
PDMは、会社の運営方針に大きく影響を与えるシステムです。そのため、PDMを導入する際は、トライアルを利用したり数ヶ月限定で利用したりと、いきなり導入に踏み切らないよう心がけましょう。
PDMツールの特性を理解した上で、「自社にとって必要十分な機能が搭載されているのか」を考えながら本導入に踏み切ることが大切です。
4.運用体制を整える
PDMを導入した当初はツールの活用方法がわからず、現場に大きな負担を与えてしまうことがあります。そのため、ツール用のマニュアルを作成するなど、運用体制を整え、全従業員がスムーズに利用できるよう準備を進めましょう。
また、場合によっては、ツールに強い人材を採用しPDM導入を併走してもらいながら運用体制を整えることも検討してください。
PLMシステムで成功させるポイント
PLMシステムを導入する場合、次の2つのポイントを意識することが重要です。
ここでは、2つの成功ポイントについて詳しく解説します。
各種業務システムとの連携を意識する
PLMは、さまざまなシステムと連携することで効果を発揮します。
たとえば、SCMと連携することで、材料の調達から発送までのデータをより詳細まで管理できますし、ERPと連携すれば、開発スケジュールや製造に必要なコストなど財務部門に必要なデータをリアルタイムで共有でき、生産までのスピードを大幅に短縮できます。
このように、複数システムを連携することでより効果を発揮するため、他のシステムと連携しやすい拡張性の高いPLMを導入することが重要です。
小規模からはじめる
PLMを導入する場合、小規模からはじめることが重要です。いきなり高額なシステムを導入してしまうと、問題が発生したときに対応しきれないケースがあるためです。
ツールのトライアルを試したり、試しに数ヶ月導入してみたりしながら、最適なツールを探すことがおすすめです。
PDMシステムで成功させるポイント
PDMシステムを導入する際には、次の2点に注意しなければなりません。
ここでは、2つの成功ポイントについて詳しく解説しましょう。
課題を全て洗い出してから導入する
まずは、課題を洗い出してから導入に踏み切りましょう。自社の現状を把握し、データ管理の課題を明確にする必要があります。
たとえば、部署間でのデータ共有がうまくいっていない場合は、遠隔地からシステムにアクセスできる機能があるPDMシステムを導入すると良いでしょう。このように、事前に自社の課題を洗い出し、抱えている問題を解決するのに最適なPDMシステムを導入することが重要です。
小規模からはじめる
PDMの導入において、一気に導入を進めてしまうと多くのコストを必要とします。また、現場にシステムを浸透させるのが難しく、システムを使わない人が出てしまうケースもあります。
そのため、最初は小規模で導入を進め、現場からのフィードバックを受けながらシステムを調整していくことが重要です。
おすすめの高品質PLMソフトウェア
最後に、PLMにおすすめのソフトウェアを紹介します。
PTC:Windchill(ウィンチル)
Windchill(ウィンチル)とは、PTC(パラメトリック・テクノロジー・コーポレーション)社が提供する製造業の製品開発において必要な情報管理を行うシステムです。正式には「PTC Windchill」とも呼ばれています。
製品の企画から生産までのワークフローや部品表、コスト管理、品質管理ができる機能が備えられています。Windchillの導入によって、後戻りのない設計や開発が可能になるため、生産性の向上を期待できます。
Windchillには次のような機能があります。
- 製品データの一元管理機能
- CADとBOMの連携機能
- キーワード検索機能
- 文書管理機能
- 閲覧機能
- CADデータ集約機能
- 変更管理機能
- 工程管理機能
Windchillでは、製品開発に関するデータの一元管理や文書の電子化の実現による業務改善が期待できます。さらに、コストの最適化による無駄な経費の発見と削減に役立ちます。
これからPLMシステムの導入を検討されている方は、この機会にWindchillの導入を考えてみてください。
他のPLMサービスに関しては下記記事でも解説しています。
PLMとPDMの違いについてまとめ
PLMが製品の企画から販売までのプロセスを対象とした概念であるのに対して、PDMは開発・設計データの管理に特化したシステムです。PLMを導入することで、製品の品質向上・業務時間の短縮を図ることができます。これに対して認証取得の効率化や業務プロセスの標準化を進められるのがPDMです。
つまり、PLMとPDMを同時に導入する場合、もれなくダブりなく自社の求める機能を満たしている必要があります。今回お伝えした内容を参考に、PLMとPDMの特徴を理解して、自社に必要なシステムはどんなものなのか確認し導入を進めてみてください。