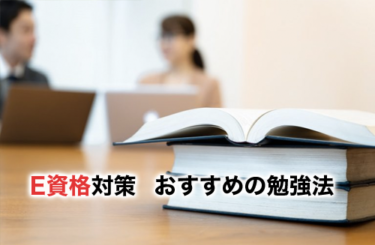最近注目されている、ディープラーニングに関する資格には「E資格」と「G検定」があります。
それぞれの特徴や違いや、自分が求めているものはどちらなのか知りたいという方もいることでしょう。
今回は、E資格とG検定の特徴や、それぞれの資格をおすすめする人について解説します。
E資格とは
E資格とは、一般財団法人ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、ディープラーニングに関するスキルを証明する資格です。
E資格の「E」は「Engineer」の略であり、エンジニア向けの内容です。
そのため、試験内容としてプログラミングの実技などの深い知識が要求されます。
近年、ディープラーニングは成長が著しい産業であるため、スキルを保有する人材の需要は高く、今後もますます注目されるといわれています。
また、ディープラーニングに特化した資格はそれほど多くないため、G検定同様に転職活動の際には他の人との差別化を図ることができるなど、転職にも有利になります。
E資格のメリット
E資格・G検定に共通するメリットについては後述しますが、特にE資格を取得することによるメリットは次のとおりです。
- プログラミング技術など、エンジニアとして現場に役立つ知識を得られる
- 合格者コミュニティで業界内の人脈を広げられる
これらにより、AI業界でエンジニアとして活躍したいエンジニアにとっては恩恵を受けられる資格といえます。
E資格の試験概要
E資格はCBT(Computer Based Testing)方式で行われる試験で、会場にある端末で受講することができます。
また、試験日は毎年8月と2月の年2回です。次回の試験日は次の通りです。
- 2023年8月25日(金)
- 2023年8月26日(土)
- 2023年8月27日(日)
また、後述しますが、E資格は試験範囲(シラバス)の改訂が頻繁に行われます。
そのため、どの受験日程がどのシラバスなのかを把握しておかないと、勉強した範囲外の内容が出題されてしまうことになるため注意が必要です。
G検定とは
E資格とよく似た資格に「G検定」があります。
G検定の「G」は「Generalist」の略称で、こちらも同じくJDLAが認定するディープラーニング向けのスキル証明に役立つ資格です。
E資格がエンジニア向けの資格である一方、G検定はビジネス向けの資格という違いがあります。
また、E資格は後述する「JDLA認定プログラム」の受講が受験資格になりますが、G検定には受験資格などはありません。
E資格に比べると難易度も低くなっています。そのため、まずはG検定に合格して、ステップアップとしてE資格取得を目指すという方もいます。
G検定のメリット
G検定のメリットは主に次のものが挙げられます。
- 受験資格がないためすぐにでも受験できる
- 受験費用が安い(E資格の半額以下)
そのため、E資格よりも手軽に受験しやすい資格だといえます。
G検定の試験概要
G検定はIBT(Internet Based Testing)方式で行われる試験で、インターネットに接続できる端末であればどこでも受講することができます。
また、次回の試験日は次のとおりです。
- 2023年9月9日(土)13:00~15:00
- 2023年11月10日(金)16:00~18:00
- 2023年11月11日(土)13:00~15:00
E資格とG検定の違い
先ほどそれぞれ解説したように、E資格とG検定の違いは、E資格が主にエンジニア向けであるのに対し、G検定はビジネススキル中心である点です。
E資格がディープラーニング自体を生み出すために必要なスキルであり、G資格はディープラーニングの「活用方法」に重点を置いた内容です。
また、E資格とG検定では、次の点が大きく異なります。
- 受験資格
- 出題形式
- 受験場所
これらについて詳しく解説しましょう。
受験資格
E資格とG検定では、受験資格が大きく異なります。
G検定には受験資格が設けられていないため誰でも受験することができますが、E資格には受験資格が設けられています。
E資格の受験資格は「JDLA認定プログラムの講座修了すること」であり、長いと数ヶ月かかるセミナーを受講する必要があります。
そのため、E資格は既に知識や経験がある人でも、すぐに受けることはできません。
「JDLA認定プログラム」の基本情報や必要性については、後半で解説します。
出題形式
E資格とG検定はどちらも選択式の試験ですが、問題数が異なります。
E資格は100問程度であるのに対し、G検定は220問出題されます。
どちらも試験時間は120分ですが、E資格の方は計算問題など、1問あたりより深く考えさせられる問題が多くなっています。
受験場所
E資格はCBT方式であるため、会場に行ってコンピュータで試験を受ける形式です。
一方で、G検定はIBT方式であるため、会場に行かなくても、インターネットが接続されている環境であればどの端末でも受講できます。
E資格・G検定を取得するメリット
E資格・G検定はどちらもAIに関係するスキルを保有する証明になるような資格ですが、取得することで次にあげるような共通したメリットがあります。
- AI業界に転職しやすくなる
- 名刺やプロフィールにロゴが使える
それぞれについて解説しましょう。
AI業界に転職しやすくなる
AI業界は成長市場であり、エンジニアの需要も高まっています。
しかし、AIの実務経験がある場合を除き、AIのスキルを証明するための資格は少なく、未経験者にとっては転職のハードルが高くなっています。
また、E資格やG検定は転職の際に積極採用条件になっているほど、他の人との差別化がしやすい資格です。
そのため、AI業界への転職を希望する人にとっては、保有していることでメリットを得られやすい資格といえます。
名刺やプロフィールにロゴが使える
E資格とG検定の特徴として、合格すると名刺やプロフィールにロゴを使用できる点があります。
名刺交換やポートフォリオなどにロゴを使用することで、自ら伝える必要もなく、相手にAIのスキルがあることを示すことができます。
取引先や名刺交換相手がE資格やG検定のことを知っていれば、「AIに関して高いスキルを保有している人」と認識してもらえるチャンスになります。
転職活動以外では、自らのことを積極的にアピールする機会も少ないかと思うのでさりげなくアピールできるので便利です。
E資格・G検定の取得がおすすめの人
結論をお伝えすると、E資格・G検定に共通しておすすめなのは、次のような人です。
- AIに関係する職種に就職したいと考えている人
- AIの知識を体系的に身につけたい人
- AIの知識を可視化してアピールしたい人
これらの条件に当てはまる人は、E資格・G検定がおすすめです。
また、E資格とG検定それぞれに特徴があり、それに関係してさらに細かな分類ができるので、それぞれにおすすめの人についても説明します。
E資格の取得がおすすめの人
E資格の取得がおすすめの人は、エンジニアとしてAI業界で活躍することを希望する人です。
また、出題形式や難易度もG検定とは異なり、より技術的な内容に特化しています。
エンジニアとして実践で役立てられる知識を付けたいと考えている人には、E資格の方をおすすめします。
G検定の取得がおすすめの人
E資格に対して、G検定の取得がおすすめの人は、早く&予算重視で資格を取得したいと考える人です。
E資格には受験資格として長いと数ヶ月に及ぶセミナーを受講する必要があり、期間も費用もかかります。
一方で、G検定には受験資格がないため、知識が既にある人であれば受験することができます。
また、出題範囲もE資格に比べると狭いため、これから学習を始める場合にも学習時間はE資格に比べれば短時間で済ませられます。
したがって、手早く資格を取得したい人にはG検定の方をおすすめします。
E資格受験のために必要な「JDLA認定プログラム」とは?
E資格を受験するためには、「JDLA認定プログラミング」を受講する必要があります。
DLA認定プログラムは、2023年現在では19社の企業が開催しているセミナーで、シラバスや内容の充実度などをJDLAが審査し、認められたものだけが開催できます。ここからは、JDLA認定プログラムの趣旨や内容について解説します。
E資格が受験資格を設けている理由
E資格の受験のために「JDLA認定プログラム」が必須となっているのは、プログラミングの実技スキルを身につけてもらいたいからです。
E資格はディープラーニングのスキルを証明するための資格ですが、エンジニアとしてディープラーニングを取り扱うためには、PCに向き合ってコーディングしたり、システムを構築したりするなどの実務作業が発生します。
一方、E資格の試験は4択問題で出題されるCBT方式なので、プログラムを書くことはありません。
ただし、実際にはコードを書くスキルは重要になるため、JDLAとしては実技スキルも受験生にはつけて欲しいと考えているようです。
そこで登場するのがJDLA認定プログラムです。
JDLA認定プログラムでは、面直やオンラインなど形式はさまざまですが、いずれにせよプログラミングの実技を取り入れた講習が組み込まれています。
E資格の受験のためには、このプログラムの受講が必須となっています。
それによって、E資格合格者は知識だけでなく、実技演習を修了した実践的なスキルを保有している人であると証明されます。
したがって、E資格合格を証明するために必要な実技スキルを身につけてもらうために、JDLA認定プログラムは存在しているのです。
『JDLA認定プログラム』の内容
JDLA認定プログラムは、ディープラーニングの高度なスキルを身につけるための講習なので、ディープラーニングに関係するあらゆる分野の知識を身につける必要があります。
ただし、ディープラーニングの技術は年々進化し続けているので、ディープラーニングを取り扱うエンジニアに求められるスキルも年々変化します。
それに合わせてE資格のシラバス(試験範囲)は頻繁に更新されるので、実際に受験する際には受験する回と受けようとしているセミナーがどのシラバスを適用しているか確認しましょう。
E資格取得を目指す人にもG検定の勉強をおすすめする理由
E資格とG検定は出題範囲や試験内容が異なりますが、E資格を取得する人にとって、G検定の勉強をすることは効果的です。
一見すると、畑違いなものに思えたり、目的に対して遠回りだと思われたりしがちですが、そうではありません。その理由は、次のとおりです。
- 出題範囲が似ている
- E資格の過去問は公開されない
ここからは、それらの理由について説明します。
出題範囲が似ている
E資格とG検定はどちらもAIに関係するスキルを証明する資格であり、同じ団体(日本ディープラーニング協会)が主催しているため出題範囲が似ています。
G検定はビジネススキルがメインなので、AIを取り巻く環境や応用例など、知識やリテラシーに関する出題が中心となります。
AIの知識を体系的に理解するためには、こういったG検定の知識が必須になるため、E資格の取得を目指す人にとってもG検定の勉強がおすすめです。
E資格の過去問が公開されていない
E資格は、過去問が公開されていません。理由は後述しますが、過去問が公開されていない以上、試験勉強の王道である「過去問対策」ができなくなります。
そこで、出題範囲が近いG検定の勉強をすることがおすすめです。
G検定の場合は、公式サイトに例題も用意されているため、学習の効果確認まで行うことができるので、出題範囲が近いことに加えて、過去問対策ができるというメリットがあります。
そのため、過去問が公開されていないE資格の勉強の過程としてG検定の勉強を組み込むことが有効になります。
E資格の過去問が公開されていない理由
メリットやE資格の目的などがわかったら、「まずは過去問に目を通して傾向をつかもう」と思う方も多いかもしれません。
しかし、多くの資格試験における王道の勉強方法である「過去問対策」はE資格ではできません。
なぜなら、E資格の過去問は公開されていないからです。その理由は次のとおりです。
- JDLAが禁止している
- シラバスの変更が頻繁
JDLAが禁止しているから
E資格の過去問が公開されていないのは、単純に情報がないからというわけではなく、主催団体であるJDLAが「過去問を公開すること」を禁止事項としているからです。
そのため、JDLAの公式ページだけでなく、インターネットで検索しても過去問はヒットしません。
シラバスの変更が頻繁
JDLAが過去問の公開を禁止しているかというと、「頻繁にシラバスが変更になるから」です。
ディープラーニングを取り巻く機械学習やAIの分野は技術進歩が活発で、ディープラーニングを仕事にしているエンジニアにとっては日々新たな知識を求められます。
それに伴い、E資格の試験範囲(シラバス)についても頻繁に変更になるため、数年前の過去問はかなり古い内容・スキルになっている可能性があります。
受験を志す人が、古い知識を一生懸命習得しても、受検当日にはガラッと内容が変わってしまっていたら、主催のJDLAも受験者も損してしまいかねません。
そうならないよう、E資格では例年過去問を公開していないのです。
まとめ
E資格とG検定は、AI業界での活躍を目指す人にとっておすすめの資格です。
大きく分けると、E資格はエンジニア向け、G検定は広くAI業界を志望するビジネスマン向けの資格です。
また、E資格は深い知識を問われる資格であり、G検定は比較的手早く受講できる資格です。
具体的に資格の取得を検討している人は、共通点や異なる点があるので、自分の目的にあった資格を選ぶようにしてください。
AIを活用した業務やDXを進めたいとお考えの企業では、AIに関する知識を深める必要があるかもしれません。
AIプロジェクトを進めるために必要なことを相談していただけます。
企業向けにAIコンサルティングサービスを提供しており、経験豊富なコンサルタントが直接ご連絡いたします。何でもお気軽にお問い合わせください。