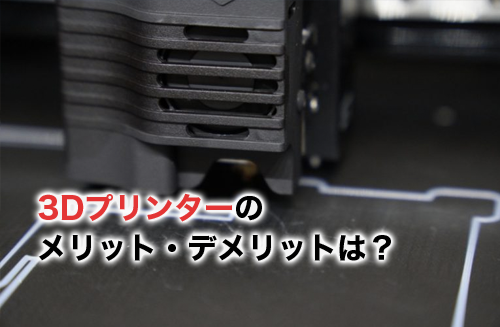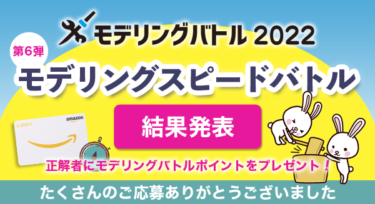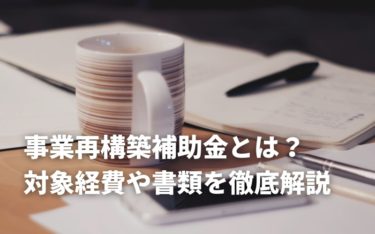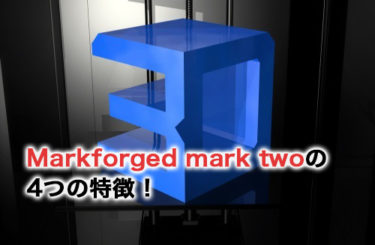3Dプリンターとは、CADなどで作成したデータをもとに、立体を作成する機械のことです。
素材となる「フィラメント」には樹脂や金属、石膏などさまざまなものがあり、さまざまな表現ができるようになりました。
近頃は3Dプリンターで住宅を作る企業も存在しており、そういったニュースを見たことがある方で、3Dプリンターに興味を持った方も少なくないでしょう。
一方で、3Dプリンターを使用することにはデメリットがあると感じている方も少なくありません。
果たして、3Dプリンターにはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
今回は、3Dプリンターを導入するメリット・デメリットについて紹介します。
また、3Dプリンター方式ごとのメリット・デメリットについても紹介しますので、3Dプリンターに興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
3Dプリンターとは?定義は?
まずは、3Dプリンターの定義を確認しましょう。
3Dプリンターとは、3DCGやモデリングソフト等を使用して設計したSTLデータをもとに立体モデルを制作する機械のことです。
一般的な「プリンター」は、制作したデータをもとに紙に対してインクを垂らし、実物として表現します。
一方、3Dプリンターでは、データをスライスした2次元の層を1枚ずつ重ねて立体モデルを制作していきます。
薄い層を1枚ずつ積み重ねていきながら、指定したモデルに近づくように出力していくプリンターが3Dプリンターと呼ばれているのです。
3Dプリンターには「光造形方式」「粉末固着方式」などさまざまな造形方式がありますが、3Dデータを出力する機械のことをまとめて3Dプリンターと呼びます。
3Dプリンターについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
3Dプリンターを導入するデメリット・注意点
多くの分野で活躍している3Dプリンターですが、場合によっては導入においてデメリットを感じることもあります。
ここでは、導入する際のデメリットや注意点について詳しく解説します。
導入コストがかかる
1つ目のデメリットは、導入コストがかかることです。
3Dプリンターは、方式や製品の質によっても値段が大きく異なりますが、大幅に費用がかかります。
具体的には、個人が使用する上で満足のいくスペックのものを購入すると20〜30万円ほど、法人が使用する場合は300万円〜400万円ほどの費用がかかります。
こういった導入コストの高さを懸念し3Dプリンター導入に踏み切れないケースは多いです。
用途によっては今後運用していく中で、初期費用を回収できることも多いですが、個人〜中小規模で3Dプリンターを導入したい場合には、予算がかけられず導入が進まないケースもあるでしょう。
なお、3Dプリンターの価格が詳しく知りたい場合は、こちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ランニングコストがかかる
2つ目のデメリットは、ランニングコストがかかることです。
3Dプリンターを運用する際、定期的なメンテナンスは避けられませんし、出力に必要な素材を用意する際にもコストがかかります。
イメージとしては、業務用のプリンターにおけるトナーやインク交換よりも高い費用が発生することになり、そういったコストのことを考えて導入に踏み切れないケースもあるでしょう。
大量生産には適さない
3つ目のデメリットは、大量生産に適さないことです。
3Dプリンターを使ってものを作るのには時間がかかります。
一例ですが、20×20cmのものを作るのに10時間程度の時間を必要とすることもあり、大量生産には向いていないでしょう。
とはいえ、同じデータのものを多種類展開する場合には、3Dプリンターが役立ちます。
3Dプリンターの中には金属、樹脂、石膏などさまざまな素材を扱えるものがあるため、製造するものや数量によっては3Dプリンターを検討することも視野に入れましょう。
製品として使用する場合強度に問題がある
4つ目のデメリットは、製品として使用する場合に強度面の問題があることです。
3Dプリンターは、原材料となる樹脂や金属を1層ずつ積み重ねて造形しています。
そのため、層と層の結合部分が弱点となることが多く、耐久性に問題が発生する傾向があります。
また、熱や光で結合部分を強化する3Dプリンターもありますが、経年劣化に弱いことが特徴です。
大きさを確認するなど、試作品として利用する場合には問題ない可能性も多いですが、実際に製品として使用する場合には3Dプリンター以外の製造方法を適用すると良いでしょう。
3Dプリンターを導入するメリット
デメリットがある一方で、3Dプリンターを導入するメリットもあります。
ここでは、3Dプリンターを利用する主なメリットを4つ解説します。
試作開発にかかる時間を短縮できる
1つ目のメリットは、試作品開発にかかる期間を大幅に削減できる点です。
試作品を開発する場合、メーカーへ外注し発送されるまでに数日から数週間ほどの期間が必要となります。
しかし、3Dプリンターを使用すれば、簡単な試作品なら5〜10時間ほどで制作でき、準備期間もほとんど必要ありません。
また、3Dデータにミスがあった場合にも素早く修正し、新たな出力物を制作できます。
このように、試作開発に時間をかけることなく、スピーディーにモデルを作れる点は大きなメリットではないでしょうか?
開発コストを削減できる
2つ目のメリットは、開発コストを削減できることです。
一般的に、試作品を外注する場合は、メーカーとの打ち合わせ、実際の制作にかかる費用などを必要としていました。
ところが、3Dプリンターで試作プロセスを内製できれば、これらの外注費用が必要なくなります。
また、試作品にミスが発生した場合にも、素早く修正できるでしょう。
アイデアをすぐに形として確認できる
3つ目のメリットは、アイデアをすぐに形として確認できることです。
3Dプリンターで試作品を制作する場合、思いついたアイデアを気軽に試せるため、新たなアイデアを生み出す難易度が下がります。
また、開発のプレゼンテーションで3Dプリンターの施策を使用することで、コストを削減しつつアイデアに関するコミュニケーションが図れるでしょう。
とはいえ、3Dプリンターで製品を出力する場合、3Dプリンター用のデータを作成する必要があります。
データの作成方法について理解していない方は、以下の記事を参考にしてみてください。
在庫が不要
4つ目のメリットは、在庫が不要であることです。
3Dプリンターで試作品を制作する場合は、フィラメントを溶かして形状を制作します。
そのため、仮に制作でフィラメントが余ったとしても、新たなデータに利用できるでしょう。
また、通常フィラメントは薄い円形で保管されるため、ストックするスペースも必要なくなります。
そういった点でも、大幅なコスト削減につながるのではないでしょうか?
3Dプリンター方式ごとのデメリット
3Dプリンターには光造形、粉末熱結、粉末固着など、さまざまな方式の種類があります。
それぞれ、熱、接着剤、光で接着するという共通点はありますが、それぞれのプリンターごとに異なるメリット・デメリットがあります。
ここでは、3Dプリンターの方式ごとのデメリットについて詳しく解説します。
熱溶解積層方式のデメリット
熱熔解積層方式の3Dプリンターは、主に一般消費者向けに低価格で流通しています。
熱で溶けるABSやPLAなどの素材を使用して、造形していくタイプの3Dプリンターとなっています。
この熱熔解積層方式の3Dプリンターには、大きく3つのデメリットがあります。
細かいテクスチャを表現できない
1つ目のデメリットは、細かいテクスチャを表現できないことです。
熱溶解積層方式では、熱で溶かし液体状になったフィラメントで出力物を制作していきます。
そのため、シンプルな制作物しか作れず、細かいテクスチャを表現することは難しいです。
層と層が脆い
2つ目のデメリットは、層と層が脆いことです。
強い衝撃を与えると、切断されたように壊れてしまうことがあり、実際に使用する製品としては強度を保てないことが多いです。
サポート材の除去に時間がかかる
3つ目のデメリットは、サポート材の除去に時間がかかることです。
サポート材とは、積層時に重力に負けないよう支えるパーツで、モデルを制作した後に除去しなければなりません。
しかし、ABSやPLAは熱で溶けてくっついていることがあり、他の方式の3Dプリンターよりもサポート材が除去できないケースが多いです。
光造形方式のデメリット
光造形方式とは、液状の樹脂に紫外線をあて、硬化させることで立体を制作する3Dプリンターです。
こちらは、SLA(Stereo Lithography Apparatus)と呼ばれることもあり、最も古い歴史のある3Dプリンターとなっています。
この方式の3Dプリンターのデメリットは大きく3つあります。
仕上がりまでに時間がかかる
1つ目のデメリットは、仕上がりまでに時間がかかることです。
液体を硬化させる場合、積層型の3Dプリンターよりも時間がかかります。
そのため、納期がある試作品の場合にはタイトなスケジュールになってしまうことがあります。
材料費が高い
2つ目のデメリットは、材料費が高いことです。
そのため、コストパフォーマンスを意識した制作には向きません。
有毒性がある
3つ目のデメリットは、有毒性があることです。
使用上の注意を守れば問題なく利用できますが、しっかりと説明書を読まずに使用すると、人体に有毒な成分が発生してしまいます。
粉末熱結方式のデメリット
粉末燃結方式は、粉末状の材料にレーザーを照射して焼き固めて成形する3Dプリンターです。3DプリンターによってはSLS(Selective Laser Sintering)と記載されていることもあります。
粉末燃結方式の3Dプリンターを活用するデメリットは大きく2つあります。
取り扱いに注意が必要
1つ目のデメリットは、取り扱いに注意する必要があることです。
他の3Dプリンターと異なり、粉末を扱うため、保存方法について検討する必要があります。
モデルの表面のクオリティが低い
2つ目のデメリットは、モデルの表面のクオリティが低いことです。
出力したままの状態では耐久性は高いものの、表面が粉っぽい印象で、製品として使用することは難しいでしょう。
粉末固着方式のデメリット
粉末固着方式とは、石膏などの粉末の材料を敷き詰め、そこに接着剤を散布することで固める3Dプリンターです。
主なデメリットは3つあります。
強度が保てない
1つ目のデメリットは、強度が保てないことです。
こちらの3Dプリンターは、石膏の粉末を接着剤で固めて造形します。
そのため、他のプリンターと比較して破損しやすくなっています。
粉末を処理できる環境が必要
2つ目のデメリットは、粉末を処理できる環境が必要なことです。
制作物が粉末に埋もれた状態でプリントされるため、刷毛やエアーなど余分な粉末を除去する必要が出てきます。
また、粉が舞い上がっても掃除ができる環境を用意しておかなければなりません。
造形の精度が低い
3つ目のデメリットは、造形の精度が低いことです。
粉末固着方式で作られた造形物は表面がザラザラとした質感で、他の3Dプリンターと比較すると精度が低くなりがちです。
また、精密な構造で造形する場合には後処理で破損してしまうことがあります。
インクジェット方式のデメリット
インクジェット方式とは、一般的な印刷用プリンターを派生させた方式の3Dプリンターです。
インクジェットヘッドから噴射した樹脂を紫外線で固めて積層していきます。
インクジェット方式の3Dプリンターのデメリットは大きく3つあります。
太陽光で劣化しやすい
1つ目のデメリットは、太陽光で劣化しやすいことです。
インクジェット方式では紫外線を使用して成形していきます。
そのため、太陽光が当たる環境では劣化しやすくなってしまいます。
製造コストが高い
2つ目のデメリットは、サポート材を使用するため、製造コストが高いことです。
素材の消費量が大きく、コストが高くなってしまいます。
匂いが発生する
3つ目のデメリットは、匂いが発生することです。
他の方式と比べてきつい匂いを発生するため、動かしている環境に長期間いると体調不良を引き起こしてしまうことがあります。
3Dプリンター方式ごとのメリット
前述したように、3Dプリンターにはそれぞれ方式ごとのデメリットが存在します。
それぞれの方式にデメリットがあることは仕方ないこととして、プリンターを選ぶ際はメリットに目を向け、活用状況に最適な3Dプリンターを選ぶことが大切です。
ここでは、3Dプリンター方式ごとのメリットについて詳しく解説します。
なお、おすすめの3Dプリンターについてはこちらの記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
熱溶解積層方式のメリット
熱溶解積層方式のメリットは大きく3つあります。
安価な機種が多い
1つ目のメリットは、安価な機種が多いことです。
エントリーモデルの場合、5万円ほどである程度のクオリティで出力できる3Dプリンターを購入できます。
プラスチック製品に近い造形物を制作できる
2つ目のメリットは、プラスチック製品に近い造形物を制作できることです。
ABSやPLAで出力し、実際の製品に近い色味を再現できるため、試作としても役立ちます。
メンテナンスしやすい
3つ目のメリットは、構造がシンプルでメンテナンスがしやすいことです。
故障の原因がわかりやすく、どの部分を修理に出せば良いのかがわかります。
光造形方式のメリット
光造形方式のメリットは2つあります。
造形精度が高い
1つ目のメリットは、造形精度が高いことです。
積層痕が目立ちづらく滑らかな表面に仕上がります。
また、表面が綺麗な状態で出力されるため、仕上がりのクオリティ自体も高くなります。
透明度の高い造形物を作れる
2つ目のメリットは、透明度の高い造形物を作れることです。
アクリル系の樹脂を使用したプリンターの場合、研磨やコーティングを行うことで、高い透明度を実現できます。
これは、他の方式では再現できません。
粉末熱結方式のメリット
粉末熱結方式のメリットは主に3つあります。
材料の自由度が高い
1つ目のメリットは、材料の自由度が高いことです。
レーザー照射によって粉末を焼き固めていくため、ナイロン、セラミック、金属など粉末同士が結合するさまざまな素材を活用できます。
耐久性が高い
2つ目のメリットは、耐久性が高い点です。
粉末同士がしっかり結合するため、耐久度の高い造形が実現可能です。
サポート材が不要
3つ目のメリットは、サポート材が不要なことです。
素材が樹脂の場合に限りますが、材料のロスを軽減できるほか、中空造形など複雑な形状のものも製作できます。
粉末固着方式のメリット
粉末固着方式のメリットは主に3つあります。
カラー造形が可能
1つ目のメリットは、カラー造形が可能な点です。
CMYKで接着剤に色をつけることで、フルカラーの立体を製作できます。
そのため、デザインの確認や建築モデル、フィギュアの製作にも役立ちます。
造形のスピードが速い
2つ目のメリットは、造形のスピードが速いことです。
比較的サイズの大きい造形物だとしても、他よりも短納期で製作できます。
ランニングコストが安い
3つ目のメリットは、ランニングコストが安いことです。
一般的には1キロ3,000円程度の材料費がかかりますが、粉末固着方式で石膏を使用する場合、1キロ500~1,000円程度で購入可能です。
インクジェット方式のメリット
インクジェット方式のメリットは主に3つあります。
精密な造形が可能
1つ目のメリットは、精密な造形が可能な点です。
インクジェット方式ではノズルから微量の樹脂を噴射可能です。
積層ピッチが細かくなるため、高精細な造形を可能としています。
複数の素材を混ぜられる
2つ目のメリットは、複数の素材を混ぜられる点です。
ノズルが複数ある3Dプリンターを使用すれば、さまざまな表現が可能となります。
装置の費用が安い
3つ目のメリットは、装置の費用が安いことです。
また、3Dプリンター以外に必要な設備もほとんどないため、導入時のコストが抑えられます。
3Dプリンターの選び方
上記でさまざまな3Dプリンターを紹介しました。
しかし、多くの方式がある中で、「どの3Dプリンターを選べば良いの」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は、次の4つの基準で選ぶことをおすすめします。
- 3Dプリンターの造形方式
- 使える材質(材料・素材)
- 3Dプリンターの精度(造形精度)
- 3Dプリンターの造形サイズ
選び方について、詳しくは以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
3Dプリンターのメリット・デメリットについて詳しく解説しました。
3Dプリンターにはさまざまな種類のものがあるため、メリット・デメリットを把握した上で用途に最適なものを選ぶことが重要です。
他にも3Dプリンターについてのさまざまな記事を用意しているので、他の記事も参考に、3Dプリンターについての知識を深めてみてください。